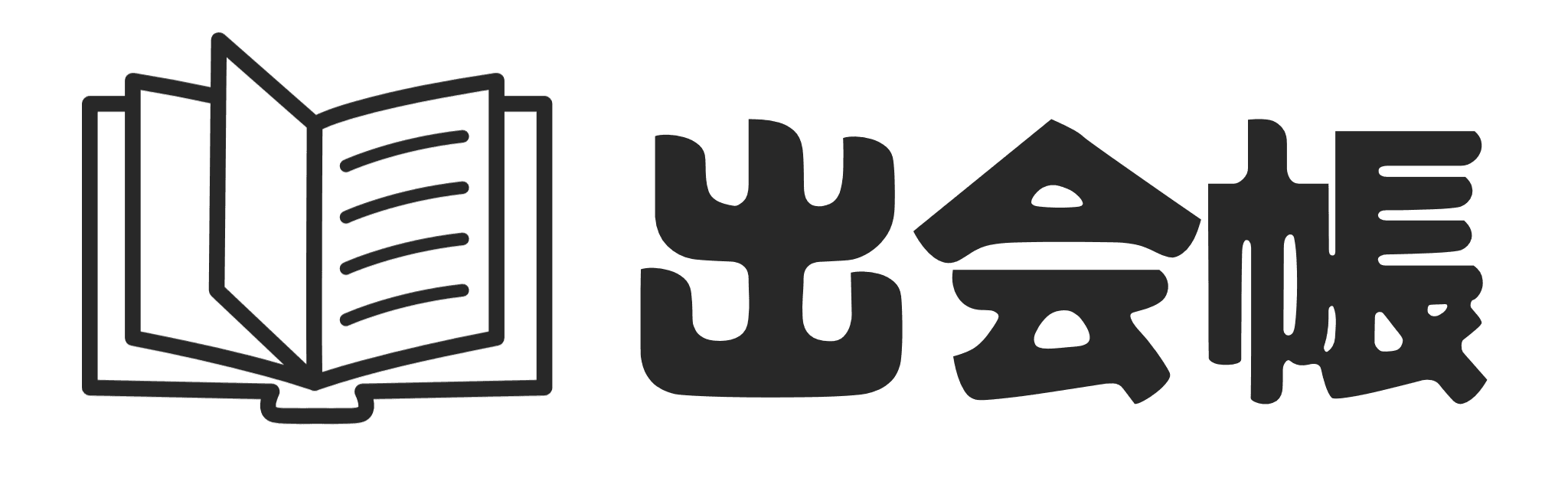「美しい」という感情は、そこにあるものを「ある」と認識させる感情です。「美しい」と思わなければ、そこにあるものは、「なくてもいいもの」なのです。
皆に出て、人は数多くの人とすれ違います。すれ違うだけで、その一々を意識しません。「すれ違うだけの人の群れ」は、「なくてもいいもの」なのです。その数が少なければ。ただ「人がいるな」程度のもので、それ以上はなにも感じません。その数が多くなりすぎでおつかったりするようになると、「こんな人の群れはなくなればいい」と思います。つまり、「なくてもいいもの」なのです。ところが、そんな人の群れの中で、時々「なにか」を見つけます。だから「今日すごく素敵な人を見た」などということになるのです。
ふつうのよさは「ふつうがいい」と自覚したときに感じることだ。ふつうでないと思う日々を自覚して人間は生きているから「ふつう」と自覚できることは幸せな感触がある。
余計に輝かず、立ち位置をわきまえ、端整であって美しく、そしてふつうである。自己を認めることで輝きを得る。他をうらやむことが醜さとなる。ふつうという定義は日本人の思いが収束していく先にある。
輝き過ぎることを気恥ずかしく思う気持ちをよくわかっている。時計やジュエリーはそれらが放つ光で選ぶものだと思うが、人はよく自分より強い輝きを身に着けようとしてしまう。そうすると自分の欲や願望が表に露出されてしまう。本当は自分のなかにもつ光の強さと同じ輝きのものを身につけることが美しいのだ。
千利休は「わび茶」を提唱し、粗末な道具しかないことを詫びる心から発し、祖末なものであるからこそ道具の組み合わせには気を使い、もてなしの段取りは完璧で、意図的で自信にあふれていたそうです。
デザインされたものとは違い、あえてださいと思えてしまうような日常のもので豊かに生活したり、人をもてなすことは、高いセンスを必要とします。
人間は、すぐ調子にのってしまう生き物で、ちょっとした”立場の優位”を感じると、急にエラくなったりしてしまう。飛行機の中でもファーストクラスでは、ただ単に人よりいっぱいお金を払っただけなのに、エコノミーの客が”下界の人々”などに見えてしまいがち。いや人はたぶんどんな些細なことでも、どんな的ハズレなことでも、優越感を感じる場面では人が変わる、そういう生き物なのだろう。
外見より中身で選ばれるべきだ。と考える人は多いが、それは大きな誤解であることを知るべきだ。外見こそが日々の努力の証拠なのである。「私はこんな仕事ができます」「私にはこんな中身があります」というようなことは既に”過去の実績”でしかない。それに比べて、日々いかに研鑽をしているか、いかに努力を続けているのかというのを最初にプレゼンするのは外見でしかないのだ。体型をはじめとした各所にいかに気を遣えているかでその人のことが手に取るように分かる。中身を人に見せる・伝える媒体も、結局は外見なのだ。
高価なものを高価だからと、やたら大切に扱っている姿には、エレガントさを感じない。たぶん、人との関わりとまったく同じ、エライ人とそうでない人とを見分けてはいけないのと同様、エライ物とそうでない物を見分けた瞬間、人はどんなに物をいつくしんでも、エレガントに見えない。かえって貧しく見えてしまうのである。
人の「存在」の美顔は、容貌とは直接に関係がありません。自分の容貌をどのように解釈するかが「人の都合」で、人の美酸はその下にあります。だから、「美しい容貌を持つ、存在が醜い人」というのは、ちゃんといます。「こないだまでは”いい”と思っていたのに、最近はちっともいいとは思えない」と人に対して思うようになったら、その人の「存在」が強くなったか、その人の「存在」をあなたが「顔い」と思うようになったかのどちらかです。「存在」という言葉がややこしかったら、「ありよう」というルビをお振り下さい。
人にとって、「美貌」というのもまた、貴族的な社会特権なのでしょう。
「特権があれば生きやすくなる」というのもまた、人間の思う「都合」の一つでしかありません。
美しいものとは、合理的な出来上がり方をしているもので、その合理的の基準は、見たり聴いたりするこちらにあるものではなくて、見られたり聴かれたりするあちらがわにある。ゴキブリはゴキブリなりに生きていて、自分自身の生き方に従って合理的なフォルムを獲得しているだけで、別に俺は美しいだろうと言っているわけではありません。ゴキブリには自分の美しさを説明できないし、自分のフォルムの合理性も説明できない。ただゴキブリとして生きているだけです。その説明してくれないものを目の前にして、フォルムの合理性を発見して、それに美しいと評価を与えるのは、ゴキブリをみるこちらの思いやりです。存在する他者を容認し、肯定してしまう言葉。それが美しいなのです。
安いもので本当に良いものはない。安いわりにはいいもの、があるだけだ。良いものは確実に高い。しかし高くても悪いものはある。選ぶという行為によって審美眼を磨くほかない。
目の前に見えているものだけが見るべきすべてのものではない
自然に勝る芸術はない。つまり人間の生き様もまた芸術なのだ。
光を見るためには目があり、音を聞くためには耳があるのと同じに、人間には時間を感じとるために心というものがある。もしその心が時間を感じとらないようなときには、その時間はないも同じだ。
目はその人の魂の強さを示す。
人間は絶え間なく、その瞬間瞬間に様々な気の凹凸をかわしながら生きている。
ある区切りによって「自分の人生」を振り返る。それがない限り、「終わりを知らせる感動」は、感動として意味を持たない。我々は、人生に立ち向かわなかった人達の美意識を、あまり考えもせずに、けっこう踏襲していたりもするわけです。
「ふつう」の価値はふつうだけだったらわからない。だから日本人は揺れのなかで中心軸である「ふつう」を見いだそうとする。
情報を脚色しないということは易しくない。人は乗せられていることを知っていながら楽しんでいるということもあるのだから、
何かが欲しいと思っていると欲望が止まらずに、その欲望が永遠に続く不満足をもたらす。煩悩とは不満足である。
特別なものがなくてもいい、みたいなものが本来の幸せ
自分のことは大切だ、自分が管理しなくちゃいけない存在だし、育てている存在とも言えるし、執着はある。でも、好きか嫌いかで判断する相手ではないように思ってしまう。だって好きだろうが嫌いだろうが、どうせここにいるのだし。失敗した自分に対して「うわー!」と責めたくなることはある、がんばった自分に対して「すごいぞ!」とめたくなることもある。でも。どうせそこにいる。現実がずっとそこにある。
今をどこまでも心地よくする方法を教えてくれ、まずは時間を止めるべきだと私は思う、未来のために今を鰹節のように削るのはもううんざりだいつまでも、今そのものを丸かじりできず、それがために、だるくてだるくて、たまらなくて、削ることも適当に。
私を特別だと言じているだけじゃきっとダメなのだ、そろそろ世界にも、私を特別だと証明しなくてはいけないんだろう。子どもだから特別で、子どもだから愛されて、それが、今まで。それなら大人になったら、私、どうなるのかなあ。
言葉は印刷された文字と一緒。ぜったいに消えない。あとから必ず甦ってきて、自分を苦しめる。言葉の後悔ほど苦しいものはないということを、悪態をつきそうになったその瞬間、思い出してほしいのだ。
行動の後悔のほうがむしろやり直しがきく。言葉は自分の中にも相手の中にも印刷文字でしっかりとすりこまれていくこと、いつもいつも肝に銘じていてほしい。
よく考えると、私は観光や出張で訪れた街では、いつも音楽を聴いていませんでした。ふだんとは異なる音環境のなかで、耳を塞いでしまうことを不安に感じていたのかもしれません。逆に考えれば、地元など慣れた場所で音楽を聴くことができたのは、建物の配置や、車の通行量などを無意識のうちに予測することができていて、安心して音楽に耳を預けることができたからでしょう。
またさらに言えば、地元を歩くのは私にとってあまりにありふれた経験で、そのためいろいろな曲を聴いてそのリズムに調子を合わせて歩く、というような楽しみを足さなければ、面倒で退屈なルーティーンのように思われていたということでもあるかもしれません。
芸術とは本来、生活のなかで生まれてきたもののはずです。美術
の源泉は家や衣服の装飾に求めることができますし、舞台芸術の源泉は宗教儀式や祭礼に求めることができます。
しかし、近代において美術館やコンサートホールという制度が整えられていくことで、芸術はそのために設えられた場所で楽しむものとされ、生活から切り離された特別なものへと仕立て上げられていきます。これに対して、芸術を日常から切り離すのではなく、日常を理想化したものを芸術と捉えることを提案します。美的経験は本来、日常生活のなかでも起こりうるもので、芸術作品が与えてくれる美的経験はこれを純化したものだと考えるのです。
池や小枝はそのとき吹いてきた風に合わせて揺れるのであり、鳥の羽もそのときの空気のようすに合わせて動くのです。
つまり自然界のリズムは、そのときの状況に応ずるかたちで、微妙に調子を変えながら、しかし全体としては秩序だった動きのうちにあるのです。そのとき、反復されているものとは、個々の要素(鳥の羽であれば、決まった幅での上下運動)であるというよりも、外的な条件に応じて個々の自然の事物が動くという、環境と事物の関係性なのだ。
美術館にあるアートが完全なる芸術というのは間違っている。美術館にある作品は、ピン留めされた蝶のようなものなのだ。
それはそのアートが生まれた経緯を思えば明らかであふ。つまり、ある特権階級または裕福な人物によって制作が依頼されたアートは、コレクションとしてその人の管理する空間に溶け込むようするに苦心して制作されたものであり、そうした本来の展示の場を離れたアート、つまり美術館に収容されている断片的な、切り貼り的なアートというのは、本来のアートとは文脈が異なっていることを知らねばならない。つまり作られた”その”時代や地域、文化的な土壌はもちろん当時の社会状況などが複雑に絡み合って生まれたものなのだ。
世界各地のアートが並べられている美術館では、その空間を含めた新しい文脈を理解することに努めることが必要であり、そうすることで新しい発見があるだろう。
肉体の制約や、富や地位や身分などをすべてはぎ取っても、なお残るものが「心」である。心が大切なのである。
ある日ふと緑の美しさに、心の底から胸うたれる時があるだろう。
ある人は、それが事業に失敗して絶望して道を歩いている時かもしれない。ある人は恋人と別れて悲嘆にくれて旅に出た時かもしれない。ある人は親しい人の死に接した時かもしれない。そんなとき、水の音の美しさに、風のリズムに、海の潮音に、それらに接してほっとすることもあるだろう。
今までもこの海の潮音はあった。垣根の花は咲いていた。道ばたで無邪気に遊んでいた可愛い子供はいた。
しかし、それをしみじみと感じたことが一度だってあっただろうか、とその人は思う。その時、自分の人生の貧しさを彼らは知るに違いない。
醸し出される「穏やかさ」こそ究極の品性。
一貫してひとつのスタイルを守り続けることが大切です。人の真似をしようとすると簡単に自分自身を見失ってしまいます。
自分自身を理解して初めて自分らしいスタイルが生まれるのです。
スタイルとは自分に精神的な落ち着きを与えてくれるものです。
ホスピタリティって感謝や感激、感動ではなく、サプライズです。
多くの人は、生まれ育つ過程で、何か特定の、少ないものに固着して視野が狭くなるーと言うと言葉が悪いですが、あまり他のものに興味を広げないで、ある範囲のなかで満足するようになります。それに対して、もっと興味を広げてみましょう、とよく言われる。
小説などの物語では、「宝物を探しに行く」というのが定番のパターンです。「ない」ものを追い求めて、やがて見つけることになる。つまり「ない」から「ある」に移行するわけです。典型的には、物語というものは、不在によって、または「矢如」によって進行します。
矢如を埋める、確かにこれは小説の基本形式です。途中にいろんなハードルを仕掛けることで、解決を遅らせて、読者の関心を引き留め続ける。それに特化すると、エンターテイメント的な性格の強い作品になる。それに対し、「如を埋める」ことに直結しないというか、その脇にあるようなディテールが豊かになると、言ってみれば「純粋芸術」的性格が出てきて、しかしエンタメとしてはわかりにくいものになる。
芸術においては、無駄な時間をとることが、まさにその作品のボリューム、物量になるわけです。作品には、大きさ、長さ、情報量といった、一定の量的規模がある。芸術作品とは、目的を果たすための道具ではありません。