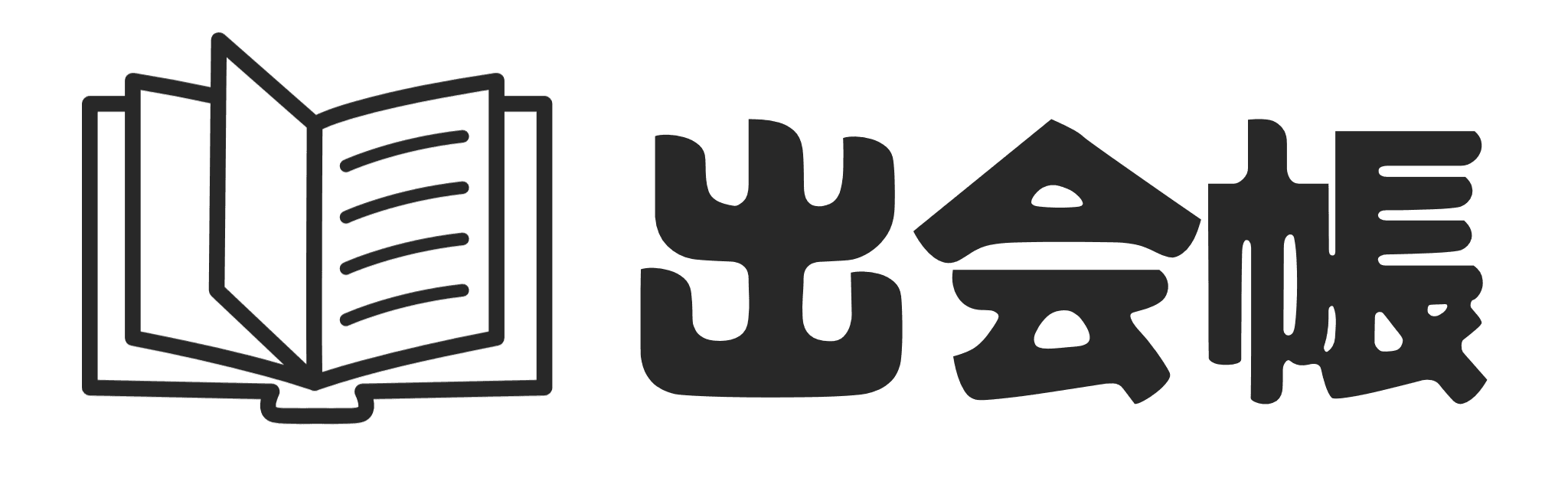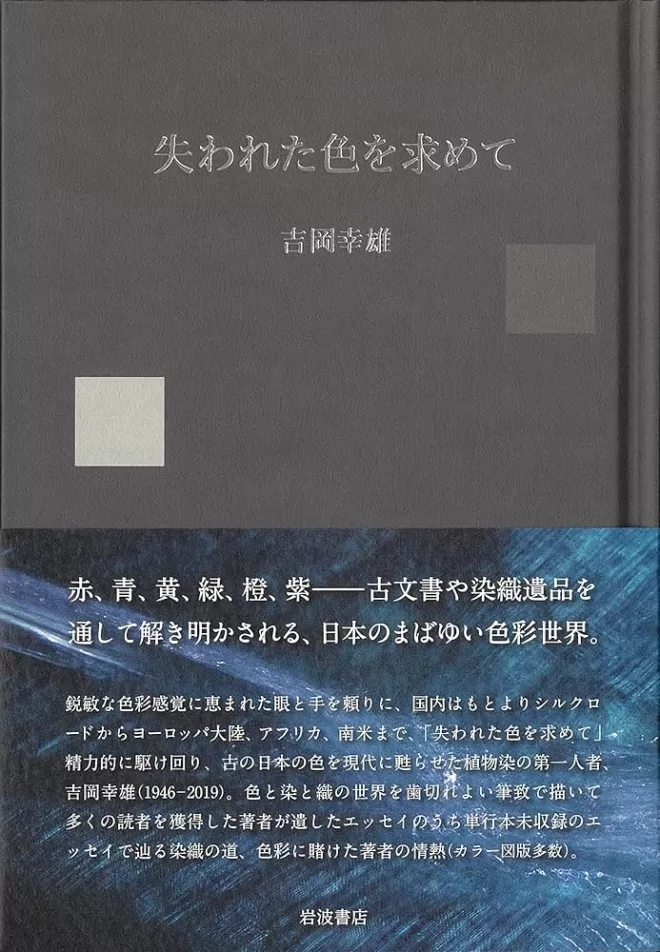私たち日本人は、自然界の一員として、その素材のもつよさと、日本の美しい四季の移ろいが醸し出す彩りを眼に焼き付けて、色というものを見なおす時代がきているのではないでしょうか。
人間は、いつの時代にも、より便利なもの、より快適なものをもとめて、技術の改良を重ね、新発見、新発明を繰り返してきました。十八世紀のイギリスに端を発した産業革命は、それまで、人間の力をもとに、牛や馬など動物の力を借りて、風や水など自然界の力を利用し、さらに新、炭などを燃料とすることで、日々ゆっくりと営んできた人間の暮らしを大きく変えました。石炭、石油、ガスなどを燃やすことでエネルギーを起こして機械を動かし、そこから化学物質を合成して新しい物質をつくりだしたのです。
日本においては、ようやく戦争の傷が癒えた一九五〇年代後半より、映画がカラーフィルムに変わりました。これまで顔料、染料という色材の表現によって色を見てきたわけですが、光の三原則、つまりこんどは光によって分光された色彩を見ることになったわけです。
さらには東京オリンピックを契機にテレビの受像機が家庭のものでもカラー化され、人びとはそれが虚像であれ実像であれ、色彩そのものを光の合成によって眼にすることになってきたのです。さらに街は明るくなり、ネオンが輝くようになって、また新しい色を見ることになっていきます。
写真、印刷もほとんどがカラー化しています。建物も木と土壁と黒瓦は大都会では消えてゆく運命にあります。高層ビルが並んで人工的な色ばかりが目立つようになりました。看板、ポスターなども、これでもかと色を競い合っています。都会を歩いていますと、自然の花草機より、そのような人工的色彩に囲まれているわけです。ある意味では華やかな時代を迎えたといえますが、色の使い方は無節操になったといえます。
服装においては、きもの姿はほとんど見られなくなり、既製品のファッションが多様に組み合わされて、道ゆく人びとは数えきれないほどの色彩をまとって歩いています。江戸時代以前の植物染であれば、公家、武家階級の人は絹の、紫や紅花染の華やかなものをまとい、庶民は藍や茶の地味な木綿や麻を着ていたのですが、そんな区別はまったくなくなり、どんな色を着てもいいのです。洋装化とともに、色もかたちも決まった既製品のなかから選ぶようになって、個性がなくなっていったといってもいいでしょう。
こうした経済成長の裏側で、きものの衰退とともに急激に「日本の色」は消失していきました。そして、日本人は、あっという間に多くの色彩感覚の共通言語を失ったのです。
たとえば京都において、春の緑をあらわすものに竹林があります。五月から六月にかけて竹の子は見る見るうちに空に向かって真っすぐに伸びてゆきます。そのとき、節ごとに茶色の皮を一枚一枚脱いでゆくのです。そして、その下からは、ほんのりと自粉をつけたような、瑞々しい青緑色の幹があらわれてきます。これを「若竹色」と称して、じつに新鮮な冴えた緑色なのです。竹は昔から日本人に親しまれて、おとぎ話になったり、生活用具の素材としても重宝されたり、と身近な植物でした。そのため、いま述べた「若竹色」のほか、さらに生長がすすんだ「青竹色」、そして、歳月を経て、「老竹色」になります。切り倒されて囲炉裏端や天井に置かれて煙に燻された竹は、「煉竹色」を示すことになります。このように、自然の移り変わりを、ひとつ竹にみても感受する日本人の心情というものが、色の名前にも伝わってくるのです。そして、古人たちの色に対する感性の豊かさと鋭さに驚嘆せざるをえないのです。
一方で人工的な色彩は、それが完成したときには美しく見えるのですが、建物や看板などは時間がたったり風雪に晒されると、たちまち醜くなってしまいます。
日本における染色の歴史をみると、秦氏による養蚕の普及と染織技術者の渡来によって、染色技術が発達しはじめた五世紀頃から、朝廷と高位な人びとのために、染色の職人たちはさかんに絹を染めていました。動物繊維である絹はさまざまな色が染まり、職人たちは競って鮮やかで華やかな色を出していったに違いありません。やがて奈良を中心にした大和朝廷ができ、さらに渡来人がつぎつぎにやってきます。それによって染めや織りにかぎらず、たとえば紙を鹿く技術などあらゆる分野に職能集団が形成されて一段と高度な文明社会が営まれてゆくことになるわけです。六世紀には色の濃淡を含め、紫、青、赤、黄、白、黒の各色を染めだす十分な染色技術が見事に完成しており、なおかつ多くの役人に供するためには、同じ色、同じ濃度で統一した大量の染色ができるまでになっていたことを、冠位十二階が示しています。
それまで染色というものは布に草で摺ったり、実や花で摺ったりというかなり原始的な方法が中心であったと考えられます。たとえば、時代は経ますが『万葉集』に「かきつはた衣に摺り付けますらをの着襲ひ猟する月は来にけり」(巻十七 大伴家持)という歌があります。杜若の花びらを摘み取って布に摺り込み、その色を楽しんだ様子がうかがえます。このような花摺りのほかに、草摺りもありました。ただ、直接布に花や草を摺ることによって得た染め色は、数日で消えるか、汚れたような色に変色してしまうし、水にあえばたちまち色が流れてしまいます。しっかり色を定着させるにはもう一段階高度な技術が求められたのでした。
技術の渡来から時代を経て、日本で独自の進化を遂げることになります。友禅染においては花や鳥の文様をあらわすのに、米糊で生地に輪郭を描き、そのなかに臙脂綿や朱の赤、藍が、群青といった青、雌黄の黄色など多彩な染料や顔料を挿し込んでいくという、いわば扇絵師本来の仕事である日本画の技を染色に応用していったのです。それまでの、天然染料の液のなかにどっぷりと浸ける技とは違って、一枚の布に自由に文様をあらわすことができて、色も筆にとりながら自由におくことができる画期的な発明だったのです。
ところで、人間はなぜ色を求めるのでしょうか。色を衣服に染めたり、生活用具に色を施したり、身近に美しい色をおきたいと願うのは、偉大な自然を自分の身に写したい、そして、自然とともに生きてゆきたいというのが人間の希望だからではないかと思われるのです。その思いは古い時代の人間ほど顕著だったのではないでしょうか。色をあらわすということは、千変万化する自然への畏怖を示すことにほかなりません。そのため、太陽や火の「赤」という色をいちばんはじめに獲得したいと思ったに違いありません。
現代の私たちは二十四時間、不夜城のごとく煌々とした光のなかで暮らしています。そのため、暗黒の世界の恐怖も、赫々とした日の光の喜びも感じることがないようです。つまり光によってものの色とかたちが見られるという畏敬の念が薄らいでいるのです。私たちの祖先、それは縄文時代までさかのぼらずとも、電気の光を得るまでの人びとというのは、日が暮れて眠り、日が昇るとともに起きて、太陽の光をほんとうにありがたいと思ったことでしょう。人は太陽によって視界を得る、ものを見ることができます。その感謝の気持ちというのは、いまの時代では考えられないほどのものではなかったのでしょうか。
人類が自然界から採集した色で染めはじめて数千年の間、工夫と進歩を重ね、歴史を作ってきた天然染料の技を、わずか百五十年の化学染料に押しやられてしまうにはあまりにも残念であるし、伝統色を見る、そして染めて美しい色を表す機会を失ってはいけないと考えている。
筆者の決意と情熱を感じる本書。いま灯火が消え掛かっている日本の色彩の伝統を守ろうとする職人の姿を改めて知り、学ぶのに相応しい本だ。