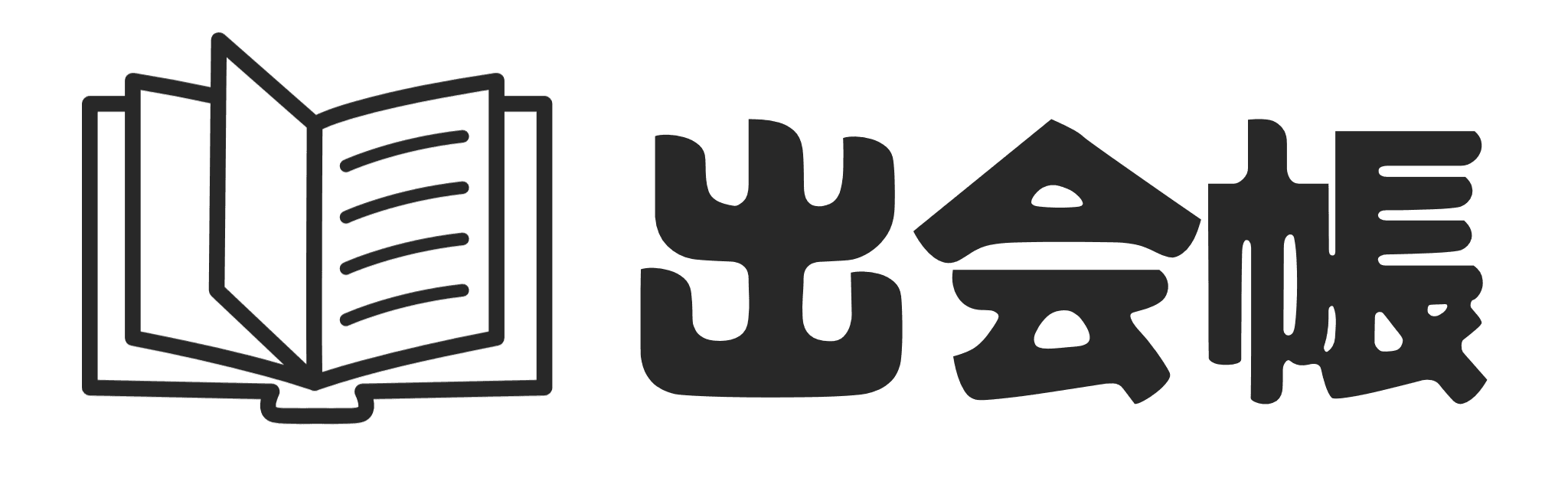この世界はあまりに苦しみに満ちていて、虐殺や不正で満ちあふれている。人間が出現するよりも前からそうだ。動物たちだって苦しんでいる。
生命は悲劇と恐怖の恐ろしいほどの堆積でもある。無数の動物種がほかの無数の種でもっておのれを養っており、それによって生物圏には一種の均衡がなりたっている。だが、その代償としてどれほどの残虐な行為が生きものにたいしてなされていることか。
自然の歴史はけっして模範となるものではない。人間の歴史はなおのことそうだ。ダーウィンの後にどんな神が存在しうるというのか。アウシュヴィッツの後にどんな神が存在しうるというのか。
財産や健康や美しさや幸福を望むことはできる。でも、徳を望むのはばかげている。卑劣漢であるか義人であるか、それを選ぶのはきみであり、ただきみだけにかかっている。まさにきみの値打ちは、きみがなにを望むかによって決まる。
父や母、学校の先生たちが言っていたこと、さらには本や新聞に書かれていたこと、そうしたことは何か間違っていたのではないだろうか?
上の世代は熱心に「理性が大切だ」「ヒューマニズムが必要だ」「民主主義を守らねばならない」「平和を維持しなければならない」と僕らに語りかけてきた。僕らにそうした理念を押し付けてきた。それを信じ、守ることを強制してきた。
だけれども、そんなものは何の役にも立たなかったではないか?ならば、近代文明には何か根本的な問題があるのではないか?彼らは親の世代にこうした疑問をぶつけたのだった。
しかし、上の世代は何も答えることはできなかった。それはそうだろう。彼らは単にそれらの理念を信じていただけだったのだから。
エジプト文明の奴隷たちは、実は結構やりがいをもっていた。
奴隷たちの生涯の目標は、奴隷のリーダーになることだった。
王様や貴族になろうとは思わず、ひたすら人に使われ続けることを選ぶ。これは現代のサラリーマン社会と酷似していないだろうか。
議論と納得とはまた別で、相手を論破しても、それで相手が自分の思うように動いてくれるわけじゃない。「理屈ではわかるんだけど、なんか感覚的に受け入れがたい」「正しいのかもしれないけれど、こいつに従うのは癪だ」とか、人間はそういう非合理的で感情的な要素で動く割合が多いからだ。
人間はみんなそれぞれ自分なりの経験と思想を持っているもので、それは違う人生を生きている他人には関われないし変えれないものだ。
あらゆる芸術は、人間が自分自身にかんするなにごとかを、ただし自分ではわかっていなかったなにごとかを認識し、再認する鏡のようなものだ。
たとえば、数学の公式の内容や背景を理解せず、これに数値をあてはめればいいだけと思っていたら、その人はその公式の奴隷である。そうなると、「分かった!」という感覚をいつまでたっても獲得できない。
したがって、理解する術も、生きる術も得られない。
ただ言われたことを言われたようにすることしかできなくなってしまう。
人間は大脳を高度に発達してきた。その優れた能力は遊動生活において思う存分に発揮されていた。
しかし、定住によって新しいものとの出会いが制限され、探索能力を絶えず活用する必要がなくなってくると、その能力が余ってしまう。
この能力の余りこそは、文明の高度の発展をもたらした。が、それと同時に退屈の可能性を与えた。
退屈するというのは人間の能力が高度に発達してきたことのしるしである。
フォードは、自社の労働者たちがフォードの車を買い、自分たちの足として、そして余暇のためにそれを用いることを望んでいた。フォードが労働者たちに十分な賃金と余暇を与えたのは、労働者たちに抜かりなく働いてもらうためだけではない。そうして稼いだお金で労働者たちに自社製品を買ってもらう。そしてレジャーを楽しんでもらう。
19世紀の資本主義は人間の肉体を資本に転化する術を見出した。
20世紀の資本主義は余暇を資本に転化する術を見出したのだ。
読書とは、「文脈」のなかで紡ぐものだ。たとえば、書店に行くと、そのとき気になっていることによって、目につく本が変わる。仕事に熱中しているときは仕事に役立つ知識を求めるかもしれないし、家庭の問題に悩んでいるときは家庭の問題解決に役立つ本を読みたくなるかもしれない。読みたい本を選ぶことは、自分の気になる「文脈」を取り入れることでもある。
1冊の本のなかにはさまざまな「文脈」が収められている。だとすれば、ある本を読んだことがきっかけで、好きな作家という文脈を見つけたり、好きなジャンルという新しい文脈を見つけるかもしれない。たった1冊の読書であっても、その本のなかには、作者が生きてきた文脈が詰まっている。
本のなかには、私たちが欲望していることを知らない知が存在している。
知は常に未知であり、私たちは「何を知りたいのか」を知らない。何を読みたいのか、私たちは分かっていない。何を欲望しているのか、私たちは分かっていないのだ。
倫理や教養は、常に過去や社会といった、自分の外部への知識を前提とする。しかしそのような外部への知識を得るには、そもそも持っている文化資本が必要である。知識の前では歴然として経済資本・文化資本の差異が見える。
見よ、今日も、かの蒼空に飛行機の高く飛べるを。
給仕づとめの少年が
たまに非番の日曜日、
肺病やみの母親とたつた二人の家にて、ひとりせつせとリイダアの独学をする眼の疲れ・・・・・・
見よ、今日も、かの蒼空に飛行機の高く飛べるを。
第二次世界大戦で日本軍の占領している中国・上海地区に空襲をかけにきた一機のサンダーヴォルト型米軍戦闘機が日本の対空砲火によって撃墜された。
そのパイロットの操縦席から数枚のクラシック音楽のレコードが見つかったという。
決死の戦場にレコードを積んでくる兵士の生き方と、今の日本の無力感に打ちひしがれた若者を比べて、どちらが生きることを大切にしていたと思うだろうか。
旅の初日にはこんな冗談を言ったとか、二日目のお昼を食べたときにはこんなことを感じたとか、旅の断片を思い出しながら、そのひとつひとつに輝きを見る。それは複雑にカットされたダイヤモンドをいろんな角度から見て、輝きを楽しむのと同じことです。
人生の出来事というのは、そのように多面的に楽しむことができる。
たとえば、戦争を描いた長編小説があるとして、戦争の悲惨さを訴えるとか、戦争反対、というのがその小説の大きな意味、わかりやすいメッセージだとしましょう。しかし作者は、そうしたメッセージを伝えるための「説得の手段」として長々と小説を書いているわけではありません。戦争で不幸を経験するたくさんの例によって、メッセージを強くしようとして長備小説が長くなっているわけではないのです。
むしろそこで提示されるのは、戦争が起きることのやむを得なさであったり、悲惨な状況においても何かの風景に見出される希望であったり、戦争というものの複雑さであって、大筋としては戦争の悪を告発しているのだとしても、それだけにはまとめられないものがある。
戦争というのは人間にとって、ひとつの巨大な「問題」です。その「問題」の複雑さを、具体的な描写を通して、まさに複雑さとして提示しているのが戦争小説だと言える。
自分自身もまた誰かにとって他者なのだから、自分がひとつの解釈を持つことは、その存在と結びついた実践だということになる。
精神的にしっかりするとは、根拠づけられた思考ができるようになると共に、それだけでは不十分で、ものごとに対し、良かれ悪しかれ鈍感になることだと思います。慣れるということです。結局、絶対的な根拠づけはできないということを受け入れる。世界には複数の人間がいて、全員が納得する解はありえない(自然科学は、「科学的に考えるならば」という条件つきの平面においてその理想を実現するかに見えますが、人間が生きる世界はその平面のみでできているわけではない)。それが体感としてわかるには、年月がかかるものです。
加齢によって指が硬く、ゴワゴワになっていくように、精神も耐性を持つようになる。
退屈と向き合うことを余儀なくされた人類は文化や文明と呼ばれるものを発達させてきた。そうして、たとえば芸術が生まれた。あるいは衣食住を工夫し、生を飾るようになった。人間は知恵を絞りながら、人々の心を豊かにする営みを考案してきた。
人々は社会をより豊かなものにしようと努力してきた。
なのにそれが実現したら人は逆に不幸になる。
それだったら、社会をより豊かなものにしようと努力する必要などない。
社会的不正などそのままにしておけばいい。豊かさなど目指さず、惨めな生活を続けさせておけばいい。
なぜと言って、不正をただそうとする営みが実現を見たら、結局人々は不幸になるというのだから。